日記発見からの道のり
- 日記の発見
- 原因の調査
- 『立命館学園新聞』「高野さんの〝死〟」
- 「カッコよ安らかにねむれ─」
- 全共闘機関紙での詩の掲載
- 『那須文学』「高野悦子さんの手記」
- 元新潮社出版部長・大門武二氏「ピンときたタイトル」
- 映画『二十歳の原点』
- 遺品 スキー道具 本と自筆のしおり 通学定期券
1969年6月25日(水)朝、栃木県宇都宮市の栃木県庁に出勤した父・高野三郎は、次女の高野悦子が自殺したという電話連絡を地元警察を通じて受けた。


直ちに京都へ向かい、京都市上京区御前通今小路下ル馬喰町の京都府西陣警察署(現・上京警察署)で本人の身元を最終確認した。


6月26日(木)、父・三郎と、悦子の母・アイは、京都市左京区東大路通近衛上ル吉田橘町の京都大学医学部霊安室で悦子の遺体を引き取った。姉・ヒロ子、弟・昌之も遺体と対面した。


午後4時から蓮華谷火葬場でだびに付した。「家族と在京の友人たち十数人で涙ながら最後のお別れをしました」(高野三郎「失格者の弁」高野悦子『二十歳の原点』(新潮社、1971年))。この「友人」は父・三郎の友人を指しており、悦子本人の直接の友人という意味ではない。
「アイは霊安室で悦子と対面した。アイが買ってあげたワンピースと靴を身につけていた。「いっしょに買ったのですから、よく覚えています。涙も出ませんでした。呆然というか、夢の中にいるようでした。私が至らなくて、あの子にさびしい思いをさせたんじゃないでしょうか」」(臼井敏男「わが娘の「二十歳の原点」」『叛逆の時を生きて』「(朝日新聞出版、2010年))と語っている。
高野悦子の実家があった栃木県では当時、通夜・告別式より先に火葬を行う場合(前火葬)が少なくなかった。一般的にも、遠方で死亡した人の場合は、先に現地で火葬をして遺骨を持ち帰って通夜・告別式をするケースが多くあった。
蓮華谷火葬場は京都市北区大北山蓮ヶ谷町にあった京都市の火葬場である。当時の建物は現存しない。


京都市中央斎場建設後の1981年3月に休止した。建物のうち比較的新しい火葬施設(1977年建設)は災害時の使用に備えて京都市中央斎場分場として維持管理されていたが、老朽化や必要性の低下から2016年に廃止された。


跡地は京都市の大北山公園となり、古い火葬施設の建物があった一角には蓮華谷火葬場跡の「慰霊碑」が建立されている。
三郎とアイは6月26日夜、遺品を整理するために高野悦子の下宿(川越宅)に行った。ヒロ子と昌之も同行した。
「アイが悦子の下宿に行くと、バッグを買うために渡した現金は手つかずのまま筆箱に残っていた」(臼井敏男「わが娘の「二十歳の原点」」『叛逆の時を生きて』(朝日新聞出版、2010年))。部屋の窓を開けたら、小学校の校庭が見えたとされる。
遺書らしいものは見つからなかった。
しかし大学ノートなど十数冊に書きつづられた中学2年生からの日記が見つかった。最後のノートには「かるちえ」と題してあった。ノートだけでなく、広告や試験用紙の裏などに書かれた日付入りの文章やメモもあった。
☞下宿(川越宅)
悦子が日記を付けていることを三郎は全く知らなかった。アイは気付いていたが中身を見たことはなかった。
三郎は「涙でかすむ目を拭いながら一気に読み通して愕然となり」「親の私が抱いていた「悦子」と別の人間がそこにいた」(高野三郎「失格者の弁」高野悦子『二十歳の原点』(新潮社、1971年))のだった。徹夜で読んだ。アイ、ヒロ子、昌之も読んだ。
三郎は、親として何も分かってやれなかった自分がつらく、深く反省した。
高野悦子の葬儀・告別式は、7月1日(火)に実家がある栃木県西那須野町(現・那須塩原市)の宗源寺で行われた。
☞高野悦子の墓
下宿から遺書らしいものが見つからなかったこともあり、高野悦子が自殺に及んだ原因について、父・高野三郎は姉・ヒロ子らとともに、日記に名前が残っていた人を中心に京都で数多くの関係者を探し出し、個別に会って話を聞き集めた。
しかし関係者の中で高野悦子に差し迫った自殺の予兆を感じていた人は見当たらなかった。
実家がある栃木県西那須野町(現・那須塩原市)で高野悦子の掛かりつけの医師だった竹内勝次は、一つの見方として「若い人として理論的にであれ、情緒的にであれ、すがりつく人があったら悦子さんは死なずにすんだろうということ」「悦子さんはその夜、大量の睡眠薬をのんだが利かなかったということを書いている。けれども結果にはかなりの昏迷状態がきていたのにちがいない。そういう状態で外へ出た。雨が降っていたというが、そのなかで線路のそばに立ってぼんやりと電車の通るのを眺めていた。そして、ふと飛び込んでしまった…」(「西那須野町中央公民館主催読書会─高野悦子さんを囲んで」『那須文学第10号』(那須文学社、1971年))と発言した。
高野悦子がアルバイトをしていた京都国際ホテル屋上ビヤガーデンでは、同学年にあたる立命館大学法学部3年生(1967年入学)の男子アルバイトが京都府警からの問い合わせの電話に最初に出たという。
電話はビヤガーデンのパントリー付近にあり、営業開始の午後5時半から間もないころかかってきて、ビヤガーデンの現場責任者に取り次いだ。その後、その現場責任者からビヤガーデンにいた従業員やアルバイトに彼女の死亡が伝えられたという。
京都国際ホテルでは自殺原因の調査は行われなかった。ビヤガーデンの女子アルバイトの間で「付き合っている人がいて、振られたんじゃない」といったうわさが流れたにとどまった。
☞屋上ビヤガーデン
高野悦子が運動に参加した立命館大学全共闘は当時、京都大学教養部のバリケード(Cバリ)に間借りする形だった。全共闘やそのシンパの学生の間に死亡の報は早い時期に入った。
大きな衝撃が走ったが、個人的な生活面まで親しかった者はおらず、自殺原因の見当がつかなかった。
立命館大学当局では日本史学専攻が教授・岩井忠熊、専任講師・衣笠安喜、助手・山尾幸久の体制になっていた。
岩井は共産党系の雑誌で「当時の彼女と近い関係にあった学生運動のグループから連絡があり、山尾君をわずらわして会ってもらったが、彼らも自殺の原因についてまったく思いあたるところがなく、それを知りたくて、紛争以来、敵対関係にあった大学に連絡をとってきたらしい。しかし大学に心当りがあるわけはなく、話はそのままでおわってしまった」(岩井忠熊「大学の生命、教師と学生の対話…民主主義への道のり─一歴史研究者のあゆみ(20)」『人権と部落問題2002年11月号』(部落問題研究所、2002年))と振り返っている。
父・三郎は「あの娘を知る人は「あんなに朗らかな人が、どうして?、何故?」と驚きの眼で尋ねます。でも私にも答えようがないのです。当日はいつもの通りアルバイトに出かけています。下宿に戻ってから夜中の午前2時頃「チョット外出します」と声をかけて出たといいます。「真夜中の汽笛の音は一体どんな響きをもっているのでしょうか」と手記にもあるように、星空を眺め孤独に耐えかねてフト死神にとりつかれたのでしょうか。私にもわかりません」(高野三郎「失格者の弁」『那須文学第9号』(那須文学社、1970年))。
そのうえで「二十歳の原点」のあとがきに「親の私があの娘の死を、生き方を、どうスケッチしようとも身内の主観的な独断的なものでしかあり得ません。読者はそれぞれの立場で、それぞれの感慨をもたれることでしょうし、さらに私の総括からはみ出したものを御汲取りいただければ幸甚です」(高野三郎「失格者の弁」高野悦子『二十歳の原点』(新潮社、1971年))と付け加えた。
父・三郎は西那須野町長を退職したあとのころ、「線路に横たわるなんてことは正気じゃできません。おそらく意識がもうろうとしていたんでしょう。普通の状態ではなかなかそういうことにはならないでしょう。別に死ぬことに「美」を描いた心境ではないと思うんです。死への憧れというのではない。
ただ自殺する1週間ほど前はものすごく落ち込んでいたようです。眠れないとか、物を食べないとか。親の仕送りにも手を付けないんですよ。それを使うのが“イヤだ”という気持ちになっていたんです。
3、4日前から寝てないだろうし、食べてないだろうし、困ぱいの状態だったと思います。正気じゃ、あまりにもかわいそうだし、そう思いたくないですよね。そう考えてやらないとかわいそうだものね。
自殺してしまったことが良いとか悪いとか決めること自体も変なことですよね。そういう状況にある人もいるんでしょう。その辺も察してあげなけりゃね。〝あれは自殺してバカだよ〟と片づければ、こんな簡単なことはないでしょうけれども。
もう少し私が、手を差し伸べてやれなかったのかとね。でも、自殺に追いやられるような条件下に置かれたという、そういうことは夢にも思わなかったです。自殺にまで追いやられる条件下に追い詰められていたというのは、想像を絶してたんですよね。そこをもう少し分かってやれなかったのかなあ、と私は思うんです」と語っている。
特に1969年7月14日(月)付の『立命館学園新聞』が3面に掲載した論説記事の中で氏名等を特定し死去の事実に言及したことをきっかけにして、立命館大学の学生に広がったと言われている。
記事の全文は以下の通りである。ペンネーム「レスカ」で書かれているが立命館大学全共闘の関係者とみられる。
この時点で全共闘側が死去の報を知り衝撃を受けたこと、また死因について直ちに思い当たるものがないことなどがわかる。
 「高野さんの〝死〟を生きよ」
「高野さんの〝死〟を生きよ」68~69年学園闘争の中で、ぼくたちは、よく「自己否定」、その主体である「全共闘」という言葉を日常用語として使う。しかし、「自己否定」「全共闘」の言葉の持つ意味、その言葉を吐くぼくたちのレーゾン・デートルをはっきりと踏まえているのだろうか。それを踏まえてないかぎり、僕たちは、今から語ろうとする、一人の立命闘争における同志の死を単なる生物学的な死へと陥しいれ、「自己否定」、「全共闘」は単なる薄ぺらな言葉、死んだ言葉でしかなくなり、ぼくたちの思想を語らない。
中川会館封鎖、恒心館封鎖、機動隊導入で先頭になって闘っていた日本史闘争委員会3回生高野悦子さん、6月24日、下宿で自殺。それは、(直接的な原因は何であれ)死という形態をとることによってか、立命闘争、全共闘運動を貫徹できえなかったという意味において、立命闘争の内の死、立命闘争に関わり、関わった者すべての死であり、覆ってはいてもぼくたち一人一人が厳としてもっている恥部として視ねばならない。
「自己否定」の思想をぼくたちは全共闘組織運動の原点として設定する、自己否定とは、自からの存在領域をたしかめ、存在証明をいかにして得るか、そこに始点をもつ。存在はハイデッガーのいう如くには、存在それ自身としては、認知しえず、情況と自己とのかかわりの中から実践的直観として認識の第一歩は始まり、それをバネにして、存在形態(労働力商品化として外部にからめとられ歪曲されている)につきあたる。その存在形態に対する反逆をただちに準備するが、反逆こそは、自己限定に他ならない。(具体的な学園闘争では、ここからここまでが自らの領域であるという〝占拠〟となって発現する)しかしながら自己限定は、単なる他者と自己の区別にすぎず、自己限定は自己権力と高められる。(個別学園闘争から全国学園闘争への転化は、その過程として位置づけられる)
かかる過程において、 「自己否定」は、自己限定-自己権力へと不断の円環の体系を成就する。
そうであるならば、「自己否定」-自己権力の思想は、自己と全共闘組織を無媒介的に連関させるのではなく、全共闘→反-全共闘→全共闘という全共闘と自己との葛藤の中からしか、同一地平を見い出し得ないのである。
自己と目標が一致する組織の運動は、ほとんど100%善であり、その組織に敵対するものは100%悪であるという、「100%善玉、100%悪玉主義」に対しては、ぼくたちは、従来、反スターリニズム、直接民主主義などを組織原則として貫徹するべきだと主張してきたが、「自己否定」の思想、その主体としての全共闘の運動は、それらをもっともよく実現する可能性がある。しかし反面、少しでも、「自己否定」の過程が断絶したり、それが意識化されてないとするならば、「自己否定」する自己との乖離はまぬがれ得ない。全共闘運動は、高い意識性と思想性が要求されるのである。
高野さんの死は、まさに自己と全共闘運動の乖離の極限状況だといえる。自己限定-自己権力へ至る手段である「全共闘」が自己の内では「自己否定」的にとらえるにもかかわらず、現実的に「自己否定」の過程が中断する時「全共闘」は自己に敵対する。
かかる二律背反を死でもって清算した〝高野さんの死〟を生きる者としてぼくたちを位置づけるとするならば、ぼくたちは「自己否定」を全共闘組織・運動の中で貫らぬく以外に道はない。(「ある視角─「自己否定」の思想」『立命館学園新聞昭和44年7月14日』(立命館大学新聞社、1969年))。
[本ホームページで文中を朱記した。記事中で死亡場所が「下宿」とあるのは誤りである。]
高野悦子の三十五日法要は1969年7月28日(月)、京都の宗仙寺で営まれた。原田方で一緒に下宿していた友人やワンゲル部の部員らも参列した。
宗仙寺は京都市下京区高倉通五条下ル堺町にある寺院。京都で数少ない曹洞宗である。


高野悦子の戒名「高学院純心法悦大姉」が入った位牌を管理している記録がある。

宗仙寺で現在、位牌が管理されているのは祠堂殿ならびに本堂東側の2か所である。


父・高野三郎は1976年に「昭和44年6月、あのいまわしい時から6年余の歳月が経ちました。昨年は個人の七回忌にあたりましたので、命日の6月24日には永代供養をお願いしてある京都の宗仙寺に夫妻で回向をしてまいりました」(高野三郎「あとがき」高野悦子『二十歳の原点ノート』(新潮社、1976年)、同『二十歳の原点ノート[新装版]』(カンゼン、2009年))と書いている。
法要の際、礼状を兼ねた「カッコよ安らかにねむれ─」と題した三つ折りのしおりが、参列した高野悦子の友人や知人に対して遺族から渡された。
このしおりが日記に関する初めての印刷物であり、その構成内容は『二十歳の原点』(新潮社、1971年)に至るまで影響している。貴重な資料を関係者が保管していた。
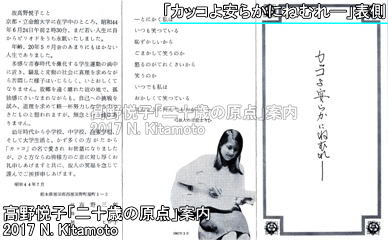

☞二十歳の原点巻末・高野悦子略歴「愛称「カッコ」」
京都・立命館大学に在学中のところ、昭和44年6月24日午前2時30分、まだ若い人生に自からピリオドをうち永眠いたしました。
年齢、20年5ヵ月余のあまりにもはかない人生でありました。
多感な青春時代を激化する学生運動の渦中に置き、騒乱と変動の社会に真理を求めながら苦悶した様子はいじらしく、いとおしくてなりません。故郷を遠く離れた彼の地で、孤独感にさいなまれながらも、自己への挑戦を試み、道理を求めて精一杯努力しながら力つきたものと想われますが、無念という他はありません。
幼年時代から小学校、中学校、高等学校、そして大学生活と、かず多くの方がたから「カッコ」の名で愛されお世話になりましたが、ひと方ならぬ皆様方のご恩に対し厚くお礼申しあげますと共に、故人の冥福を念じて謹んでご挨拶申しあげます。
昭和44年7月
また日記の記述から「とにかく私はいつも笑っている…」(1969年6月21日)の一節が抜粋され、ギターの写真の切り抜きが載せられている。
内側には「-故人日記の最終頁より/44.6.22-」として「旅に出よう」の詩が無題で縦書きされている。小学校、高等学校、大学ワンゲル部で活躍する姿や小紋を着た写真が並べられている。グラフィックデザイナーの横尾忠則(1936-)やシュールレアリスムを代表する画家であるサルバドール・ダリ(スペイン、1904-1989)の作品をモチーフにしたとみられるイラストも描かれていることがわかる。
☞1969年4月10日「街に出かけよ、山に出かけよ─」
☞旅に出よう(詩)
☞ギターの写真
☞小紋を着た写真
「旅に出よう」の詩は、1969年10月10日(金)付で発行された立命館大学全共闘の機関紙『コンテスタシオン第2号』(立命館大学全学共闘会議機関紙編集委員会、1969年)4面で掲載された。しおりが元になったとみられる。
機関紙『コンテスタシオン』は立命館大学全共闘で有力だった法学部闘争委員会(法闘委)のメンバーが創刊した。したがって創刊号(1969年6月28日)の発行者は「立命館大学全学共闘会議法学部闘争委員会機関誌編集局」と記されている。
法闘委を含め立命館大学全共闘は、すでに京都大学教養部(京大Cバリ)に間借りする形となっていた。このため「僕たちの一歩は、余りにも遅過ぎる時になって始めて踏み出された。語るべき時に語らず、行うべき時に行ない得ない自らの限界は、僕たちにとっても、屈辱であり、はずかしさである」「僕たちは、自己を表出する限り、ここに怒りと悲しみと苦悩とを書くことになるし、生きようとする決意=闘争宣言を書き続ける」(「怒りと悲しみと苦悩とを─創刊にあたって」『コンテスタシオン創刊号』(立命館大学全学共闘会議法学部闘争委員会機関誌編集局、1969年))ことになった。
元・法闘委リーダーは「法闘委の運動をどう続けていこうかとみんなで議論して、〝やっぱり機関紙いるだろう〟ってなった。こういうのが好きなのが何人かいて〝じゃあ、やるか〟って割り付けして原稿を書いていった」と話す。


運動の中での党派(セクト)に対して批判的な論調だったが、党派間の対立が激しくなかったこともあり、第2号(1969年10月10日)では全共闘の「立命館大学全学共闘会議機関紙編集委員会」が発行者になった。
編集委員会メンバーの間では高野悦子の死去はすでに知られていた。「〝彼女の死をそのままにしておくのはどうだろう〟という話があって、詩を見つけてきて載せようとなった」、メンバーの一人だった元・法闘委リーダーは事情を話す。メンバーだった別の関係者は「詩は高野悦子の日本史専攻の同級生女性が頼んできた」と語っている。

『コンテスタシオン第2号』では高野悦子の死去について、同学年の法学部学生が仮名で「運動全体の低迷の中は、蔽うべくもない暗黒状況であった。その中で一人の女子学生が自らの生命の軌跡を断った。僕たちは、今、散った生命が帰ってこない以上、何をなすべきなのかと、自らに問わねばならないだろう」(「新しい闘いを前に振りかえり見て想うこと」『コンテスタシオン第2号』(立命館大学全学共闘会議機関紙編集委員会、1969年))と言及している。
この詩の掲載をめぐっては、「高野は69年6月に死去。しばらくして、立命館大全共闘機関紙「コンテスタシオン」を作っていた天野博さん(66)の元に、詩の原稿が持ち込まれた。「旅に出よう」で始まるこの詩を、高野は日記の最後に書き残していた。同年5月、立命館大全共闘は対立する共産党系学生に大学を追われ、活動家は学内に入れなくなっていた。「全共闘の終わりを象徴する気がして、迷わず載せました」(天野さん)」(「舞台をゆく─自己問い詰めた若者の聖痕─京都市上京区」『毎日新聞(大阪本社)2014年1月27日(夕刊)』(毎日新聞社、2014年))とする新聞記事がある。
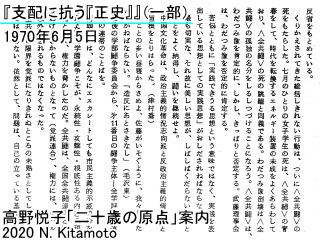 『コンテスタシオン』は第2号を最後に休刊となったが、編集委員会は翌年の1970年6月に、立命館大学での全共闘の主張や大学側極秘メモなどの資料をまとめた110ページ余りの冊子、『支配に抗う『正史』─立命館大学闘争の記録・上』を刊行した。
『コンテスタシオン』は第2号を最後に休刊となったが、編集委員会は翌年の1970年6月に、立命館大学での全共闘の主張や大学側極秘メモなどの資料をまとめた110ページ余りの冊子、『支配に抗う『正史』─立命館大学闘争の記録・上』を刊行した。
そこでも「くりかえされてきた総括しきれない行動は、ついに<全共闘>の死をもたらした。7月のひとりの女子学生の死は、<全共闘>の青春をして、時代を転換するエネルギー装置の未成をよくあらわしており、<全共闘>の死の跳躍と同義である」(「序文」『支配に抗う『正史』─立命館大学闘争の記録・上』(立命館大学「コンテスタシオン」編集委員会・法学部闘争委員会、1970年))と高野悦子の死去について改めて触れている。
その後、「『コンテスタシオン』が法闘委の機関紙として、その地歩を築く時、学園から後退した全共闘の隊列にとっては、学部運動の政治情宣を任務とするだけでなく、全学的闘争の橋頭堡として位置付けられた。従って、それは全共闘機関紙として、権力によって根拠地を奪われ、切断された闘争精神を定着させ、行為における共感の枢軸を希求するものであった。だが、告発の時代は終わっていた。
我々は、11月闘争以降停止している。個別的深化が全体性を獲得、回復する闘いの時まで、機関紙活動のみを継続させる意義を見出し得ないからである」(立命大コンテスタシオン編集委員会「立命館大・コンテスタシオン」『全共闘機関紙合同縮刷版』(全共社、1970年))と表明した。
